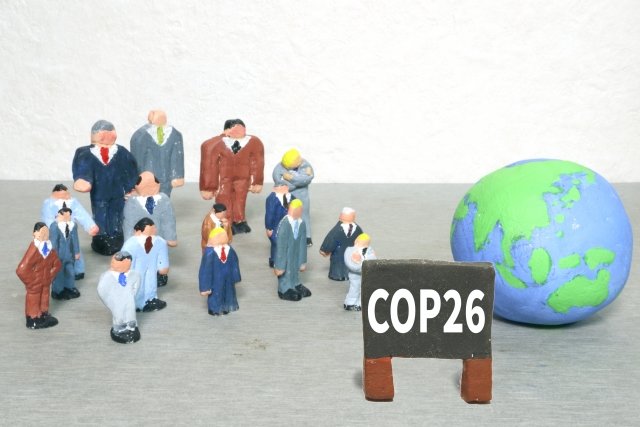
本論に入る前に
これが今年最後の研究員コラムになる。今回のコラムは「良い統合報告書」と「読みやすい統合報告書」を今年最後に書こう!とずっと考えていたので、今回はその点を書くのだが、さすがにディスクロージャー&IR総合研究所のESG/統合報告研究室の研究員として先月上旬開催されたCOP26についての考え方も述べる必要があろう、ということで本論に入る前に簡単にCOP26について考え方を述べたいと思う。
COP26は成果を上げたのか
日本であまり見られない、というより同調圧力の強い日本では「気候変動対応は当たり前!」となっているが、グローバルなメディアに目を転じると英国では「温暖な秋の気候のため、風力発電所の発電量が通常よりも少なく、また、ガス価格の高騰によりガス火力ではコスト高になるため9月6日、電力需要を満たすために古い石炭火力発電所を稼働させた。」或いは、米国では『クリーンな電気の使用量を年間4%以上増加させた電力会社に助成金を提供し、その基準を満たさない電力会社にはペナルティを課すとしてバイデン大統領が推し進めようとした「Clean Electricity Performance Program」が上院で否決された』などと、国家間における政治的に一致した方向性の決定には時間がかかるという印象だ。しかし、気候変動は何らかの物理的リスクを引き起こすと多くの人々は感じ始めていることだけは変わらない。
このような状況下でCOP26は人類と地球との関係において記念碑的な瞬間となるはずだった。しかしながら、アロク・シャーマ議長はグラスゴー気候協定の発表を前に各国代表団の間を・・・・
上記のボタンの中で、記事を読んでの感想に近いものを押してください。
(押すと色が変わります ※複数選択可)
読者の皆様からのフィードバックは執筆者の励みになります。


なお、具体的に研究員に調査してほしいテーマがありましたら、以下のコメント入力フォームからご送信ください。
※個人情報(個人名、会社名、電話番号等)は入力しないでください。
※なお返信を要する質問等につきましては、以下のお問い合わせフォームまでご連絡ください。
https://www.takara-company.co.jp/contact/