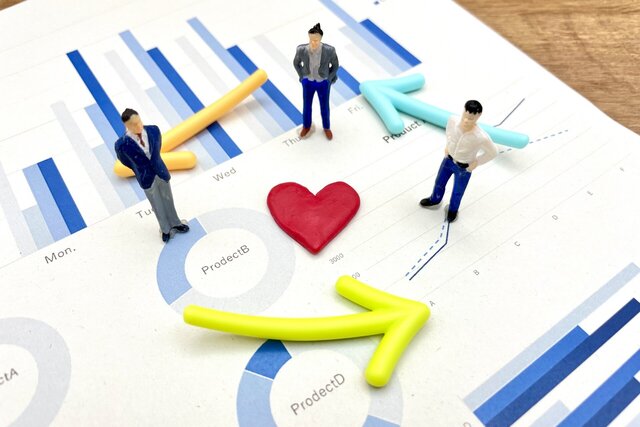
これからの統合報告に求められるもの
生成AIが猛スピードで進化を遂げ、経営や働き方に影響を与える未来を10年前に予見できた人はどの程度いたのだろうか。2014年にIIRC国際統合報告フレームワークの日本語版が発行されてから11年、企業環境は大きく変化した。気候変動や人口動態の変容、デジタル化の進展、さらにコロナ禍による価値観の揺らぎが、企業にこれまで以上に長期的視点での経営を迫っている。同時に、資本市場では機関投資家を中心として、短期的な業績にとどまらず、中長期的な企業価値を支える非財務要素への関心が高まってきた。こうした潮流の中で統合報告書は、企業とステークホルダーを結ぶ重要な対話の場として存在感を増し、上場企業を中心に急速に普及してきたと言える。
一方で、近年はトランプ大統領を象徴とする反ESGの動きが注目を集めている。サステナビリティ情報開示に真摯に向き合ってきた日本企業からすれば、この潮流は逆風だと感じるだろう。しかしこの潮流は、行き過ぎたESGブームに冷静な視点をもたらし、本来のサステナビリティ経営とは何かを問い直す機会になっているとも言える。つまり、単なる批判ではなく、形骸化した取り組みを是正し、企業が自らのパーパスと事業戦略を結びつけて、持続可能性を実践する方向へと軌道修正する力にもなり得る、ということだ。いまや統合報告書は、企業が自社の価値創造ストーリーを誠実に語り、投資家や従業員、社会との対話を深めるための不可欠な媒体へと進化している。形式的な報告にとどまらず、未来に向けた挑戦や課題を率直に共有する姿勢こそが、これからの統合報告に求められる真の価値であろう。
変更された日経統合報告書アワード審査基準、企業はどう受け止めるべきか
統合報告書の発行企業が増加の一途を辿る中、自社の統合報告書が財務資本提供者である機関投資家にとって意義あるものになっているのかを評価するひとつの手段として、日経統合報告書アワードに応募する企業も増加している。2024年度の日経統合報告書アワード参加数は496社・団体と過去最多になったそうだ。そして、2025年度は、企業価値創造に向けた具体的なビジネスモデルとガバナンスの重要性を重視するとして、審査基準を変更している。
例えば、トップマネジメントのメッセージについては「メッセージが直近1年の事業環境や経営状況を踏まえたものになっているか」の中から「直近1年」が削除され、「メッセージが事業環境や経営環境を踏まえ、経営者自らの経験・課題認識・考えに基づくメッセージ・・・・・
上記のボタンの中で、記事を読んでの感想に近いものを押してください。
(押すと色が変わります ※複数選択可)
読者の皆様からのフィードバックは執筆者の励みになります。


なお、具体的に研究員に調査してほしいテーマがありましたら、以下のコメント入力フォームからご送信ください。
※個人情報(個人名、会社名、電話番号等)は入力しないでください。
※なお返信を要する質問等につきましては、以下のお問い合わせフォームまでご連絡ください。
https://www.takara-company.co.jp/contact/